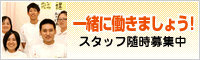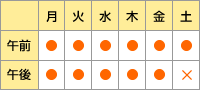福山市でスポーツ障害の時はどこに行けばいい? 股関節の痛みは、グロインペイン症候群かも?
股関節のスポーツ障害による痛みは、競技やトレーニング内容、体の使い方によってよく出現します。代表的な原因や障害を紹介します。
福山市にある”はこだ鍼灸整骨院”では最近このような股関節の痛み症状の方が増えています。
① グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群)
-
サッカー・バスケ・陸上などで多い
-
内転筋、腸腰筋、腹直筋、に負担が集中
-
キック動作、ダッシュ、切り返しで痛みが強くなる
② 股関節インピンジメント
-
股関節の骨がぶつかり合い、関節唇が損傷する
-
骨の形状異常(カム型・ピンサー型)が原因
-
⚠️股関節を深く曲げたり、捻ったりすると痛む
③ 腸腰筋炎・腱障害
-
腸腰筋の使い過ぎや柔軟性低下が原因
-
前方の付け根に痛みが出る(足を上げるときに痛い)
④ 大腿骨頭壊死・疲労骨折(稀だが注意)
-
夜間痛や安静時痛がある場合、精密検査が必要
今回は①のグロインペイン症候群について
股関節〜鼠径部(足の付け根)に痛みが出る状態の総称です
●主な症状
-
鼠径部(足の付け根)のズーンとした痛み
-
走る・蹴る・開脚・起き上がり動作で痛む
-
運動後に悪化、休むと少し楽
-
長引くと片側だけでなく両側に広がることも
●原因として
① 筋肉由来
-
内転筋(太もも内側)
-
腸腰筋
-
腹直筋・腹斜筋
→ 使いすぎ・柔軟性低下・左右差
② 股関節の問題
-
股関節の可動域制限
-
インピンジメント(FAI)
-
骨盤の歪み
③ 体幹・姿勢の問題
-
体幹が弱く、脚に負担集中
-
反り腰・骨盤前傾
④ 神経・腱の関与
-
腱炎
-
恥骨結合炎
-
軽度のヘルニア(スポーツヘルニア)
など、これらの原因が考えられ
一つの原因というより、複合的に関連しあって発生することが多く
問診や状況判断が必要になります。
対処法簡単に
〇 安静(痛みが出る動作の中止)、アイシング
-
無理な運動は中止
-
痛みを出す動作を避ける
〇 ストレッチ
-
内転筋・腸腰筋の柔軟性改善
-
股関節の可動域改善
〇 体幹・骨盤トレーニング
-
左右差の修正
-
フォーム・動作改善
また、はこだ鍼灸整骨院ではスポーツ外傷だけでなく
50歳以上の女性の方で、股関節の痛みで来院される人も多く
女性にとって股関節痛は好発部位 (よく起こる場所)になります。
早めに来られた方は施術をして改善に向かっていく方が多いです
その他の股関節痛の痛みの原因
① 変形性股関節症(最も多い)
高齢女性の股関節痛の代表格
特徴
-
歩き始めが痛い(動くと少し楽)
-
長く歩くと痛む
-
足の付け根・お尻・太もも前に痛み
-
靴下が履きにくい、爪切りがつらい
背景
-
若い頃の臼蓋形成不全(日本人女性に多い)
-
加齢・体重・筋力低下
② 大腿骨近位部骨折(見逃し注意)
転倒がなくても起こることがある
特徴
-
片側だけ強く痛い
-
体重をかけると激痛
-
歩けない/歩きにくい
-
寝返りで痛む
※骨粗鬆症がある人は特に注意
③ 大転子部痛症候群(外側が痛い)
昔「大転子滑液包炎」と呼ばれていたもの
特徴
-
股関節の外側が痛い
-
横向きで寝ると痛い
-
歩行・階段で悪化
④ 筋力低下・柔軟性低下
-
中殿筋・腸腰筋の弱化
-
姿勢変化・歩き方の変化
→ レントゲン異常がなくても痛い
見逃してはいけない原因
⑤ 関節リウマチ・炎症性疾患
-
朝のこわばりが強い
-
両側性
-
他の関節も痛む
⑥ 感染・腫瘍(まれだが重要)
-
安静時・夜間も強い痛み
-
発熱・体重減少
-
痛みが急激に悪化
いろんな原因があり
鑑別判断が必要になり
医師との連携も必要になります