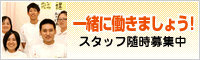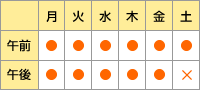肝臓と感情の関係性 心と身体は関係しあっているのか?
肝臓があたえる情緒、感情について
✅ 西洋医学的な観点
-
肝臓は「解毒」「栄養の貯蔵」「ホルモン・代謝の調整」などを担っています。
-
肝機能が落ちると、だるさ・集中力低下・気分の不安定さが出やすい。
-
アルコールの摂りすぎ、脂肪肝、肝炎などが背景にあると、気分面に影響することも。
-
肝機能が低下すると、エネルギー産生や代謝がスムーズに行われず、体がだるく疲れやすくなる
-
老廃物や毒素が体内に残ると、体調不良や倦怠感の原因にもなる
-
軽度の脂肪肝や慢性的な負担でも、疲労感が出やすい
-
イライラすると、交感神経の過緊張がおこり、その結果、血圧上昇・心拍数増加・肝臓での代謝負担増大が起こり、肝臓の血流が乱れたり、脂肪肝・肝機能障害につながる可能性もあります。
✅ 東洋医学的な観点(漢方・経絡)
-
「肝」は「血」を貯え、全身の「気」の流れをスムーズにする役割。
-
肝が乱れると「気滞(きたい)」=気の流れが滞る → 怒りっぽい・イライラ・ため息が増える。
また怒ったり、イライラしていると、肝を痛めていきます。
負のスパイラルになります
-
肝の働きが弱ると、血や気の巡りが滞り、全身のエネルギー不足を感じる
-
春は特に「肝」が影響を受けやすい季節とも言われます。
西洋医学的には「沈黙の臓器」と言われている
-
肝臓はかなりの機能が失われても自覚症状が出にくいため「沈黙の臓器」と呼ばれます。
-
つまり、血液検査や画像検査で異常が出る前から、実はダメージを受けていることもある。
-
東洋医学で肝臓は 剛臓(ごうぞう) と呼ばれることがあります。
-
「剛」は文字通り強い・しっかりしているという意味。
-
肝臓は体の中で気や血の巡りを調整する役割があり、体を支える柱のような臓器と考えられています。
西洋、東洋ともに強い臓器とあるように
検査値は「ある程度の異常」が出ないと反映されにくい
-
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP は「肝細胞が壊れたときに血液に漏れる酵素」なので、ある程度細胞破壊が起きないと数値が上がらない。
-
軽度の脂肪肝や、慢性的な負担(薬・お酒・ストレスなど)では、検査値が正常の範囲に収まることもある。
検査項目は肝臓の一部の働きしか見ていない
-
肝臓には「解毒・代謝・胆汁分泌・免疫機能」など多様な役割がありますが、ASTやALTだけではその全体をカバーできません。